
ITとビジネスが直結している現代では、そのスピードも以前とは比べものにならないほど速くなりました。
中でもシステム開発は、その波を顕著に著しているもののひとつではないでしょうか。
そこで今回は、システム開発手法の変化と、それにともなう働き方のあり方などを、株式会社ガイアックス 技術開発部 PMO木村卓央さん、株式会社ガイアックス デジタルコミュニケーション事業部 ICTソリューション事業グループ システムマネージャー 上坂太志さん、渡邉涼介さんの3人にお伺いしました。
左から順に、株式会社ガイアックス デジタルコミュニケーション事業部 ICTソリューション事業グループ システムマネージャー 上坂太志さん、株式会社ガイアックス 技術開発部 PMO木村卓央さん、
株式会社ガイアックス デジタルコミュニケーション事業部 ICTソリューション事業 渡邉涼介さん
大切なのは、顧客のニーズ。「アジャイル開発」とはどんな手法?
ICTソリューション事業グループでは、ECサイトや店舗の売り上げ向上を支援するコーディネートメディアクラウドサービス「
(木村)「システム開発のプロセスには、いくつか種類があるんです。日本でよく使われるのは『ウォーターフォール』という手法。これは、一番初めにすべての要件を洗い出して、詳細な見積もりと計画を立ててから進めていきます。この手法だと、長期間かつ重厚長大になってしまうというデメリットがあるんです。
対してアジャイル開発とは、すべての要件を洗い出すことはせず、現状で考えられる範囲のものの中で優先順位を作り、小さい計画を立てながら進めていく手法です。顧客のニーズを聞きながら、少しずつ価値を出していくのが特徴的ですね。1990年代に登場した開発プロセスで、別名『軽量型開発手法』とも呼ばれています。
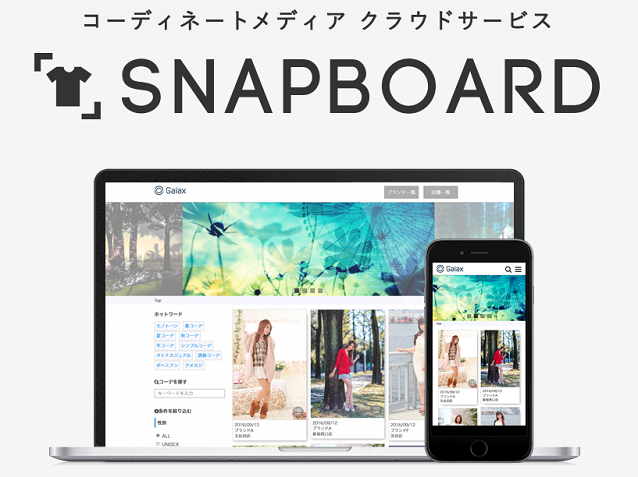
従来の「ウォーターフォール開発」とは180度違うものなんですね。木村さんは、この「アジャイル開発」の支援導入をされているそうですが・・。
(木村)以前は、依頼された仕事のシステムやソフトウェアを開発する、受託開発でエンジニアをしていたんです。
受託開発は与えられたスケジュールで仕事をこなすのですが、管理的な仕事が増えてくると、開発のスケジュールや開発の意義そのものに疑問を持ち始めました。
しかし、意見をする機会はなく、ただただ仕事をこなすのみ。
そこで従来の開発手法ではなく、もっと効率的かつ主体的に働きたいと思い、いろいろ調べていくうちに、アジャイル開発に出会いました。
まずは自分の開発チームでXP(エクストリームプログラミング。アジャイル開発手法のひとつ)やスクラム(こちらもアジャイル開発手法のひとつ)を取り入れるなどしていましたが、徐々に外部へアジャイルコーチとして指導に赴くようになりました。
現在はガイアックスでアジャイル開発手法の導入支援をしています。アジャイル開発の研修や、事業部からの支援要請でそれぞれ指導を行っています。
木村さんが現在アジャイル開発の支援指導をしているのが、デジタルコミュニケーション事業部・プロダクト開発チーム。なぜアジャイル開発を導入したのでしょうか。
(渡邉)アジャイル開発は、新規サービスの立ち上げにとても有効だと思ったからです。
前例のない新規事業は、仮説で進む内容がどうしても多く、それを従来のウォーターフォール手法で進めてしまうと、仮説が正しいのかどうかを判断できるのがずっと先のことになってしまうんです。
そうなると、そもそもこのサービスが成功するかどうかの判断も難しく、なかば博打的なことになりかねない。
アジャイル開発なら、開発の途中で細かい修正ができ、顧客のニーズもその都度取り入れることが可能です。
変化に柔軟に対応できるところがアジャイル開発の魅力的な部分ですね。

より人間味のある働き方へ。「アジャイル開発」導入のメリットと今後の課題とは
プロジェクトに適していたということですね。実際にアジャイル開発を導入してみて、作業面でどんな変化がありましたか?
(木村)アジャイル開発は「柔軟な対応ができる」ということの他にも、「開発には全員が参加する」という特徴があるんです。
ウォーターフォール開発では、プロジェクトマネージャーが顧客とニーズを考えたり、仕様を作成したりしているのですが、エンジニアはこれに一切関わらないことが多い。
アジャイル開発ではプロジェクトマネージャーを置かずに、開発に関わる全員が最初からすべての行程に参加して、意見を言い合いながら進めていきます。
ウォーターフォール開発のような分業型の作業方法だと、自分が関わる作業以外では動かない人間が出てきてしまいますが、アジャイル開発なら、全員が「なぜこのシステムを開発するのか」ということを理解しているため、責任感を持って自発的に動くことが可能になります。
(上坂)今回はアジャイル開発の中でもスクラムという開発プロセスを使っています。
これは「チーム全体でタスクをこなす」のが特徴的。木村さんがおっしゃったように、ウォーターフォール開発の分業型とはまったく違い、誰がどの分野をやってもいいんです。
そうなると、チームメンバーそれぞれが何でもできる知識が必要になりますよね。
(上坂)はい。メンバーがそれぞれの得意分野に加えて、新しい知識を増やしていくことが必要不可欠です。
もしこれが可能になれば、チーム全体としても個人としても相当なスキルアップになります。
また、「メンバー全体で仕事をこなす」ということは、「なぜこのタスクをしなければならないのか」という意味が全体で共有できるということでもあるんです。
「よく分からないけれど、与えられたから仕事をする」というスタンスよりも、「こういう理由があるから、この仕事をする」というスタンスのほうが、責任感もモチベーションも変わりますよね。
(渡邉)アジャイル開発では、「やること・やらないことリスト」を決めています。
これを決めることで、チームがどんなことに価値を置いているのか、モチベーションが上がるのかを把握することができるんです。
それにともなって個々の価値観というのも見えてきます。チームメンバーがどんなことを考えて、どんな風に日々の仕事をしたいのかをお互いに分かっていれば、フォローがしやすい。
結果、コニュニケーションが充実して、より人間味のある仕事体制ができあがってくるわけです。
お互いを尊敬・尊重し合う関係が芽生えたのも、アジャイル開発のおかげではないでしょうか。
現在、アジャイル開発を導入して1カ月ということですが、最後に今後に向けての課題や改善点などを教えてください。
(上坂)事業部の成長を目指しているので、それにはまずチーム全体の成長が課題ですね。
作業の共有化のために、タスクの可視化を徹底しているのですが、これが初めはとてもストレスで・・。
というのも、それまでは1日の仕事内容は頭の中で管理していたので、それをリスト化するという作業になかなか慣れることができませんでした。
しかし、タスクの可視化をすることで自分の仕事量を客観的に把握することができますから、エンジニアの仕事環境の改善や意識の向上にはとても有効なこと。
アジャイル開発でなければこうした改善は望めなかったのではないでしょうか。
今後はアジャイル開発のメリットを他のチームにも広げ、ゆくゆくは社外へもアピールしていきたいです。
(渡邉)まだ稼働日数が少ないこともあって、全体的な粗が目立ちます。
そこを少しずつ改善していけたらと思います。
(木村)システムの開発者はどうしても技術者目線なんです。クリエイターにありがちな、独りよがりの傾向が強くあります。しかしシステム開発において、一番大切なのは顧客のニーズ。分業型の枠組みがないアジャイル開発で、こうした意識のズレを改善していけるといいと思います。
取材協力:
株式会社ガイアックス 技術開発部 PMO木村卓央
SIer系でシステム開発を行っていたが従来型の開発手法に疑問を感じ、改善点を模索していたところ、アジャイル(当時はXP)開発に出会う。
そこからアジャイル開発をチーム導入や、外部のアジャイルコーチとして実践を重ねるなどして、各コニュニティなどで習および情報交換をしてきた。
2012年からはアジャイルコンサルタントとして、各方面へのアジャイルの導入支援や研修を行っている。
現在はガイアックスにて組織内のアジャイル開発を推進中。また、「合同会社カナタク 代表社員 アジャイルコンサルタント」の肩書も持つ。
関連サービス
「社内ノウハウの属人化や、複数ツールがあることによって情報の管理コスト上がっていませんか?社内ノウハウの蓄積や共有に特化した15機能を実装。社内ノウハウ・情報の属人化や社内システムの一本化による業務効率を改善します。
休業者へのアナログ対応により業務コストがかかったり、復職への不安から離職してしまったりしていませんか?
増える休業者の事務・連絡作業を効率化するだけではなく、育休、休職者とのやり取りをスムーズにすることで、復帰時の浦島太郎状態を回避し、定着率の大幅改善します。
「リモートで対面コミュニケーションが減った中でも、チームのモチベーションを上げながら対話の場を作りたい。」
ティール組織の理論に基づいた約29項目の「組織の強み」から自社の強み可視化します。更に、レポート結果を元に対話を促すことで、自社らしい自律的な組織進化を支援します。





